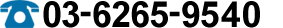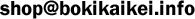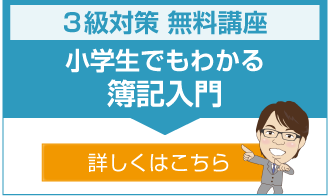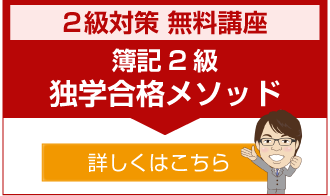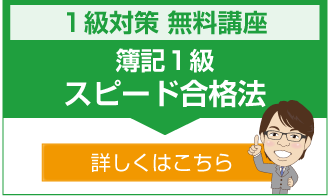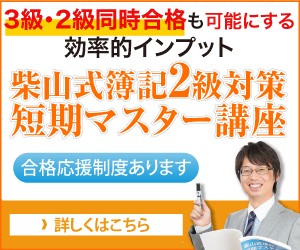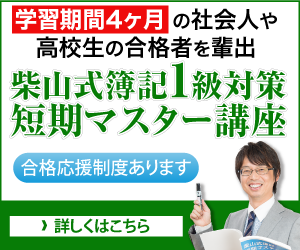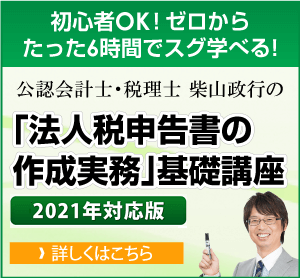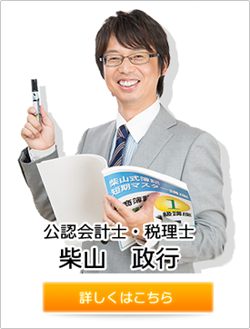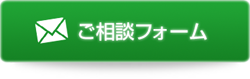簿記ャブラリ一覧
-
「売上債権」という言葉は、商売において非常に重要な概念です。 現代のビジネスでは、掛け取引(後払い取引)が多くなっています。すぐに現金で代金を受け取るのではなく、取引先に対してある程度の期間、支払いを待ってあげることで、 […]
-
この「配賦基準」という言葉は、製造間接費を各製品や部門に配分する際に使われるもので、試験でもよく出題されます。 また、工業簿記を学ぶ初心者の方々がよく悩む部分でもありますので、この機会にしっかりと理解していきましょう。 […]
-
「当座預金」とは、小切手や手形などの決済手段を利用するための口座です。 この預金は、昭和の高度成長期に登場し、現在ではその利用機会は少なくなっています。 時代の流れにより、その役割は終わりつつある預金といえるでしょう。 […]
-
このテーマは少しマニアックではありますが、現金の範囲として試験に出題される可能性もあるため、取り上げることにしました。 3級・2級の試験ではそれほど気にしなくても良いかもしれませんが、将来的に簿記一級や会計士などの資格試 […]
-
まず、「当月製品製造原価」や「当期製品製造原価」という表現について見ていきましょう。 月次決算の場合は「当月製品製造原価」、年度決算の場合は「当期製品製造原価」という表現が使われます。 この製造原価は、損益計算書における […]
-
未渡小切手と未取付小切手は簿記の学習において混同しやすい部分があるので、しっかりと違いを理解しておきましょう。 現代では電子決済が主流なので、小切手を使う機会は少なくなっていますが、簿記の試験には出題される可能性があるた […]
-
まず、「現金出納帳」の重要性についてですが、これは現金の受け払いを記録するための帳簿です。 実務においては非常に重要で、特に現金の収入や支出、残高を取引の都度記録するための補助記入帳として使われます。 重要度は、試験レベ […]
-
まずは「月次損益」です。この言葉は収益と費用に関連していて、2級の試験では重要な用語なので、重要度は星2つにしました。 では、月次損益の意味を見てみましょう。 定義としては、1ヶ月単位で行われる損益振り替えに用いられる勘 […]
-
「未渡小切手」は、2級の銀行勘定調整表などでよく見られ、決算手続きや仕訳にも影響を与えることが多いです。 また、場合によっては1級などの上級レベルの試験でも出題されることがあるので、ぜひこの機会に理解を深めてください。 […]
-
まずは「ストックオプション」という言葉からです。 最近では日経新聞やビジネス雑誌、例えばダイヤモンドや東洋経済などでもよく見かける用語です。 上場企業で多く使われているので、知っておくといいですよ。 ストックオプションは […]
-
まず「原価」という言葉ですが、これは2級レベルの資産と費用に関する重要な用語です。 資金勘定などに集計されると資産になりますし、売上原価という費用として計上されれば、完成した商品が販売されるときに「売上原価」となります。 […]
-
まずは「株式市場」についてです。 株式市場とは、いわゆる上場企業の株を売買するための市場のことを指します。 日立やトヨタのような有名な企業が上場しているんですね。 日本では東京証券取引所が代表的な株式市場ですし、海外では […]
-
まず、「資産」についてです。資産は、取引の単位を区分する勘定科目の一つです。資産のグループと考えると分かりやすいでしょう。 具体的には、現金や預金、棚卸資産、固定資産、建物などが含まれます。 会社にとって、将来収益を得る […]
-
まず、「工業簿記」についてです。これは製造業を主な事業目的とする企業が採用する簿記の方法です。 製造業やメーカー、さらには建築業なども工業簿記の対象になります。 そして、「商業簿記」や「完全工業簿記」という言葉もあります […]
-
まず、「債権者」という言葉です。 これは法律用語でもありますが、債務者(お金を借りている人)に対して一定の権利を持っている人、つまりお金を貸している側のことを指します。 例えば、会社が銀行からお金を借りている場合、会社は […]
-
まず、工業簿記でも「仕掛品」はよく聞く言葉だと思いますが、「半製品」という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。 そこで今回は、この仕掛品との違いについて説明していきます。 では、まず「半製品」についてお話ししますね。 […]
-
まず、「複式簿記」について説明します。 簿記とは、取引を帳簿に記入することを指しますが、その中でも「複式簿記」は、簿記の学習で一般的に扱われるものです。 この「複式」という言葉がつくことで、より本格的なものとなりますが、 […]