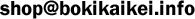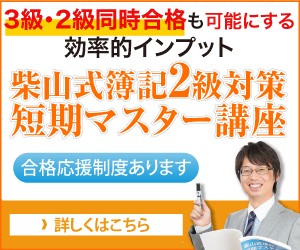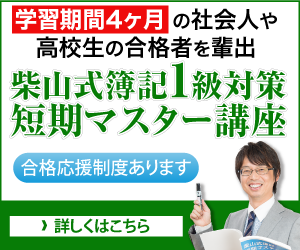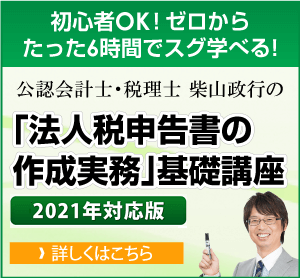石油元売り大手5社、石油精製能力を20%削減(日経13*2*14*1)
2月14日の日経一面では、東燃ゼネラルを含めた石油元売り大手の5社が
国内石油精製能力を2割程度カットするという計画とのことです。
これには政府の規制が関係していて、エネルギー供給構造高度化法という法規制によりますと、石油などの化石エネルギーの有効活用を目的として、安価な重質油から付加価値の高いガソリン・軽油などを精製する設備を一定比率設置することを義務付けているそうです。
しかしながら、このような設備の取得には多額の資金が必要なので、各社は精製設備の削減などといった対応に動いているのが現状です。
ここで基本的な話ですが、設備投資をすると、とうぜんのことながら、その設備を購入するために何億円もの支出がありますね。
設備の購入にあてた支出額は、有形固定資産と言って、投資した金額は支出した年の費用とはならず、耐用年数と呼ばれるその設備の寿命と見積もられる期間にわたって少しずつ費用化し、同時に資産としての評価額を
減らしていきます。
毎年費用化される額の事を減価償却費と言います。
ご存じの方も多いでしょう。
※機械装置を費用配分した場合
(借方) 減価償却費 ××× (貸方) 機械装置 ×××
この減価償却費は、設備の稼働が100%であろうと、50%であろうと、極端な話0%であろうと、発生する額は一定であり、必ず発生すると考えられています。
こういった費用を「固定費」とも呼びますね。
↓
※設備の利用度合いの多少にかかわらず一定額発生する費用
設備投資をしたら、この減価償却費以外にも、設備の維持費や設備の管理をする人件費など、設備自体を持つことでどうしても負担せざるを得ない追加の固定費がかかるものです。
こういったものの固定費は、ある程度の売上(需要)を見込んで生産設備を100%フル稼働することで回収することが予定されています。
もしも、この生産設備が当初の計画よりも20%少ない80%程度の稼働しかできないならば、その分売上が得られません。
また、そもそも80%程度の操業しかできないとわかっていれば、もっと設備の規模を小さくして、より少ない固定費でもよかったはずです。
つまり、固定費の規模は「その事業の器の大きさ」もあらわしているのですね。
当初の計画値に満たない操業しか出来なくても、固定費は必ず一定額かかるので、100%フル操業と実際の操業水準との差に対してかかる固定費はロスとなります。
このような操業水準の不足による固定費のロスを「操業度差異」と呼びます。
(例)A社のある工場設備は、年間5000個の製品生産を100%フル操業と予定して、それに見合った固定費として年間500万円の固定費発生を見込んでいる。
今年は景気が悪く、4000個の生産しかできなかった(80%操業度)。
しかし、固定費は500万円かかるので、1個当たり500万円÷5000個=0.1万円の固定費を予定していたところ、1000個の操業不足×0.1万円=100万円の固定費のロス、すなわちマイナスの操業度差異100万円を出してしまった。
このように、計画数量通り作れなかった時にかかる固定費のロスを把握することが、経営の実態を理解するために必要となります。
ここで、新聞記事の話に戻ると、国内全体の精製能力は規制導入前が日量480万バレルであり、ここから370万バレル程度まで削減するということで、これにともなって設備の規模が縮小され、固定費負担が軽くなる、という試算です。
その差は480万-370万=110万バレルですから、おおむね2割程度の設備カットと考えても不思議ではないですね。
設備投資の供給過剰は固定費の操業ロスとして、管理会計上、まともに企業経営を圧迫します。
ちなみに、供給過剰の工場で操業ロスを少しでも回収するために超低価格で生産を引き受けることがあることから、100円均一のビジネスにおける原価が安い原因の一つともいわれているのを聞いた事があります。
日商簿記2級の工業簿記で、操業度差異という言葉を学習しますが、今回とりあげた石油元売り大手の精製能力カットの記事は、まさにこの操業度差異にちなんだ時事テーマといえそうです。