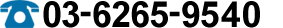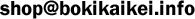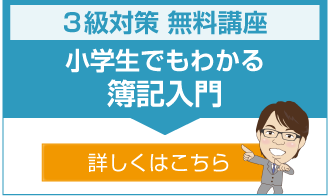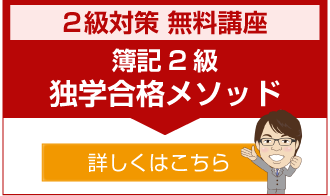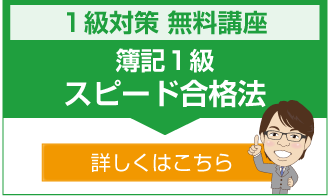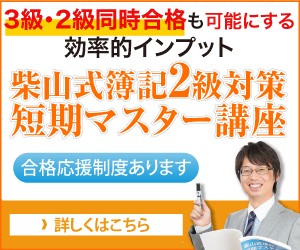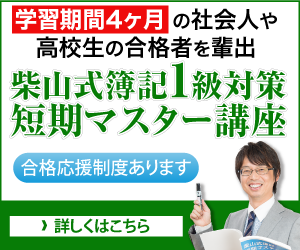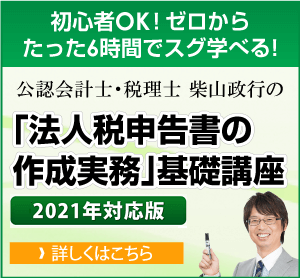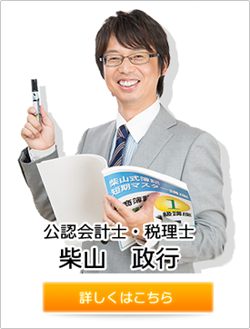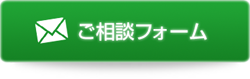貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
今回は「貸付金」と「借入金」について解説します。
これらの用語は、ビジネスの場や会計試験でよく登場し、重要な概念です。
特に、レベル3級以上の試験では重要度が高く、しっかり理解しておくことが求められます。
まず、貸付金とは、金銭を貸し付けた場合に発生するもので、会計上は資産(I資産)に分類されます。
一方、借入金とは、金銭を銀行などから借り入れた場合に発生するもので、将来の支払義務が生じるため、負債(Ⅱ負債)に分類されます。
また、これらの取引に手形が関与する場合には、「手形貸付金」や「手形借入金」という言葉が使われます。
これらは簿記の試験でもよく登場する重要な概念です。
関連語句としては、支払利息(借入金)、受取利息(貸付金)、手形貸付金、手形借入金などがあります。
これらは、貸付金や借入金に伴って発生する利息に関連する重要な項目です。
次に、貸付金と借入金が発生した際の解説をします。お金を貸す場合、貸した金額に対して利息を受け取ることになります。
この利息は「受取利息」として会計処理されます。
逆に、お金を借りる場合、借りた金額に対して利息を支払うことになり、この利息は「支払利息」として処理されます。
一般的に、企業では貸付金が生じることは少なく、もし貸付金が発生した場合、それは通常、役員や関連会社など、いわゆる身内への資金援助であることが多いです。
このような取引は税務調査で問題となることがあるため、取引の理由を明確にし、説明できる体制を整えておくことが重要です。
一方、借入金は特に不況時に注意が必要です。売上が伸びていないと、借入金の返済負担が大きくなり、返済ができなくなると企業の倒産や経営破綻につながる可能性があります。
したがって、借入金の管理は非常に慎重に行うべきです。
具体的な取引例を挙げてみましょう。たとえば、取引先に1,000,000円を貸し付ける場合、元本1,000,000円に対して2%(20,000円)の利息が発生します。
この利息分を差し引いた残額、つまり980,000円を小切手で支払うといった取引が考えられます。