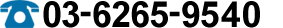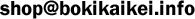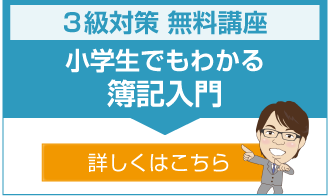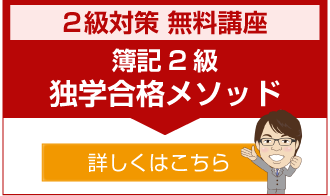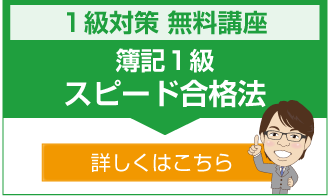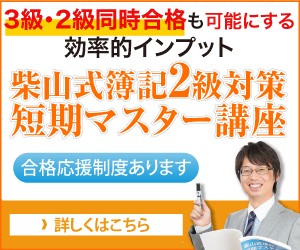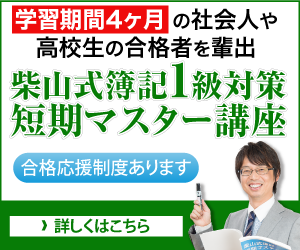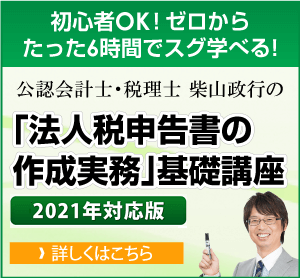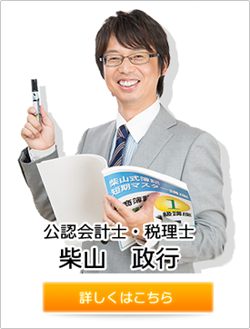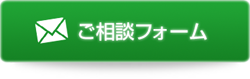サービス、商業簿記
今回は、「サービス」と「商業簿記」について解説します。
まず、「サービス」という言葉について説明します。
経済用語では、売買において相手に効用や満足を提供する形のない財を「サービス」と呼びます。
一方、法律用語ではこれを「役務」と言います。
また、サービスを提供して得た収益は、売上ではなく「役務収益」として区別されます。
会計上、サービスが問題となるのは、そのサービスがどの事業年度に行われたかという点です。
例えば、映画の前売り券を販売した場合、その映画を実際に観せるサービスが行われていなければ、映画会社は売上を計上することはできません。
具体的には、3月末決算の映画会社が3月中に前売り券を販売し、お金を受け取った場合でも、映画のサービス提供が翌月4月に行われるのであれば、その収益は来年度の役務収益として計上され、3月の決算時点では売上として計上できません。
このように、サービス提供がどの年度に行われたかを正確に把握することが重要です。決算日をまたぐ取引では、この点に注意が必要です。
次に、「商業簿記」について説明します。
「商業簿記」は、「工業簿記」と対になる概念です。
商業簿記は、完成した商品を購入して販売する企業の取引を管理するための簿記です。
商品と対比されるものに「製品」があります。製品とは、材料を加工して作り上げたもので、工業簿記で扱う完成品のことを指します。
未完成のものを加工して完成させるものが製品であり、すでに完成しているものを購入して販売するものが商品です。
商業簿記は、小売業や卸売業など、商品を仕入れて販売する業態に適用されます。
商業簿記は、簿記の中でも最も基本的な部分を扱っており、どの企業でも決算や会計処理の際に利用されます。
製品を製造して販売する企業では、工業簿記が用いられますが、それ以外にも、業種に応じた特有の簿記(例えば、農業簿記、銀行簿記など)も存在し、これらは応用簿記として分類されます。