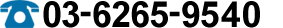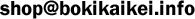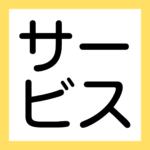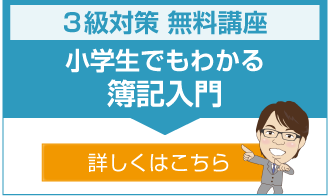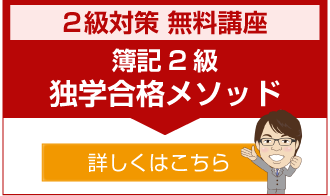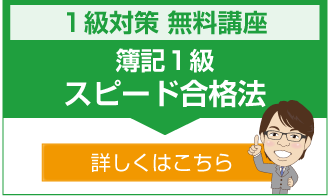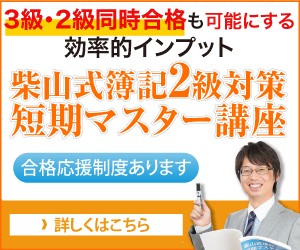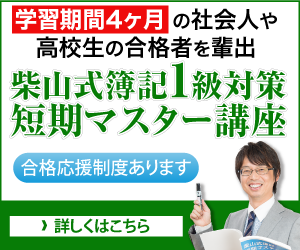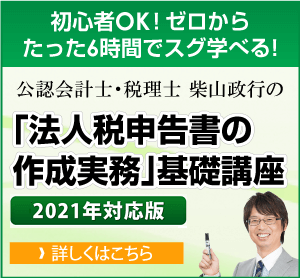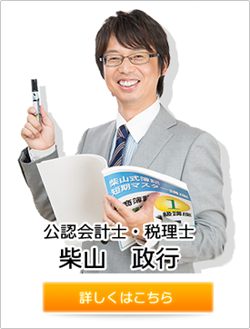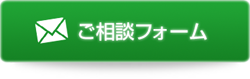手形、精算表、倒産
今回は、「手形」、「精算表」、「倒産」の3つについて解説します。
これらの用語は簿記の学習において重要な前提知識であり、ビジネス用語としてもよく使われるため、この機会にしっかりと理解しておくことをお勧めします。
まず、1つ目の「手形」についてです。
手形には主に「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。
しかし、現代のビジネスでは手形を使う機会は減少しているため、実際に見ることは少なくなっています。
約束手形とは、受取人または指図人に対して、一定の期日までに一定額を支払うことを約束する手形です。
一方、為替手形は、手形の振出人(発行者)が第3者(支払人)に対して、受取人または指図人に一定額を支払うことを委託する手形です。
商取引においては、支払いを決済するために使用されることが多く、例えば、2ヶ月後に100万円を支払うために約束手形を発行するケースなどがあります。
次に、2つ目の「精算表」について説明します。
精算表は、会計の決算処理の際に、試算表から損益計算書や貸借対照表を作成するために用いられる計算表です。
精算表には6桁精算表、8桁精算表、10桁精算表などがあり、それぞれの精算表には異なる内容が含まれます。
6桁精算表には、試算表、損益計算書、貸借対照表の借方・貸方の6つの欄があり、1枚の用紙で完結できるため、一覧性が高く、チェックがしやすいという利点があります。
8桁精算表は、6桁精算表に修正記入欄の借方・貸方が加えられたものです。
さらに、10桁精算表では、整理後試算表の借方・貸方が追加されます。試験では、特に8桁精算表がよく出題されるため、しっかり理解しておくことが重要です。
最後に、3つ目の「倒産」についてです。
倒産とは、企業や個人が債務を返済できなくなり、事業を継続できなくなる状態を指します。
倒産の手続きには、法律的な側面が関わり、主に以下のような方法があります。
破産、特別清算、会社更生、民事再生などがそれにあたります。また、企業が6ヶ月以内に2回、手形や小切手を不渡りにすると、銀行との取引ができなくなり、事実上の倒産となります。
倒産した場合、会社の清算が行われ、残った財産があれば、それを分配する「精算型」と、会社の再建を目指して手続きを行う「再建型」があります。
このように、倒産は経営破綻とも呼ばれることがありますので、関連する用語をしっかり覚えておきましょう。